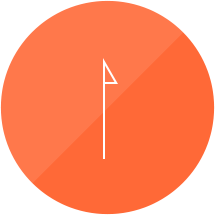小児気管支喘息
(ぜんそく)とは
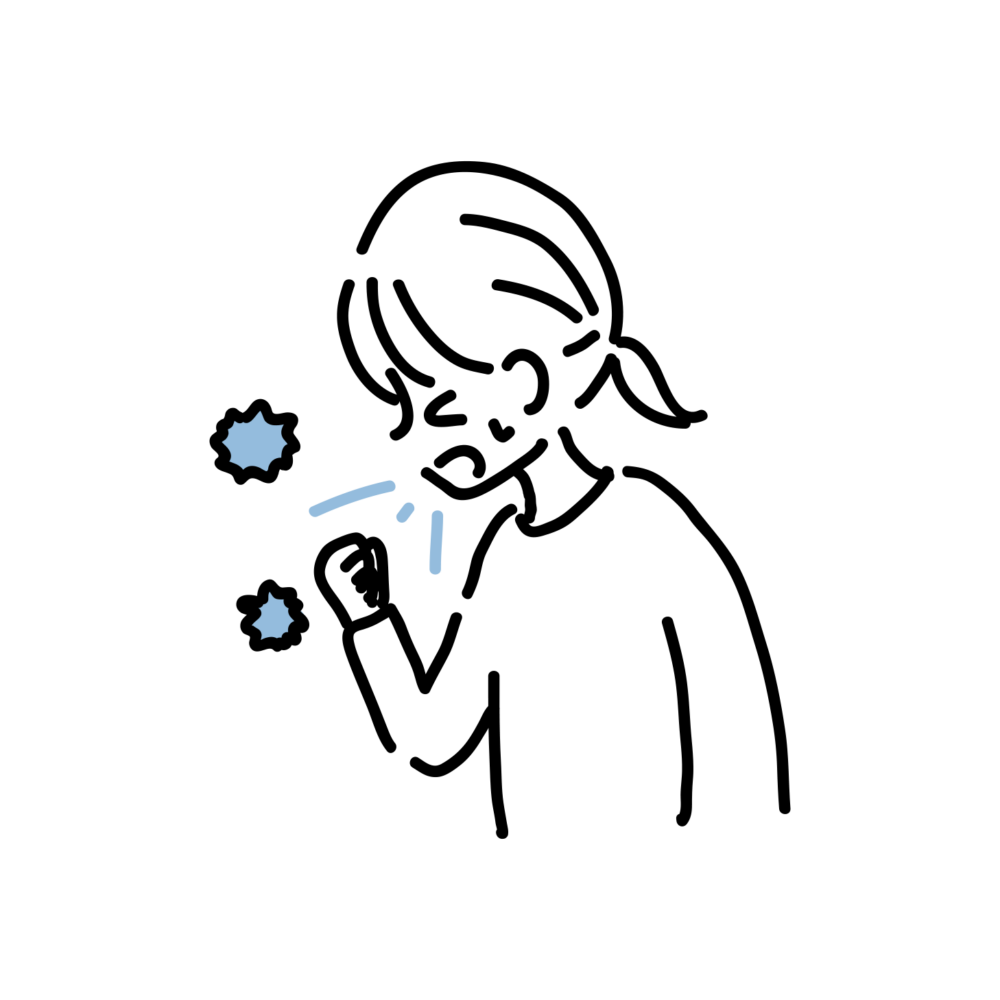
気管支喘息は、空気の通り道となっている気管支が狭くなり、呼吸が苦しくなる状態を繰り返す病気です。
「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった喘鳴や、夜間・早朝に発作が起こることが特徴です。
しかし、風邪などによる咳との区別が難しい場合や、喘鳴が他の疾患でも起こる場合があるため、慎重な診断が必要です。
当院では、喘鳴の有無、風邪以外の咳、運動時や興奮時の咳、アレルギー疾患の家族歴、アレルゲンへの曝露などを詳しく確認し、適切な診断を行います。
特に幼いお子様では、咳き込んで吐いたり、横になることを嫌がったりするだけの場合もあり、診断が難しいことがあります。
喘鳴や咳が続く場合は、早めの受診をおすすめします。
呼吸困難に至ることもあるため、迅速な対応が重要です。
小児気管支喘息の症状と特徴
気管支喘息の症状はさまざまですが、主なものには以下があります。
息苦しさ、胸の詰まり感、喘鳴(「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という音)、咳、痰などが挙げられます。
また、咳が主な症状である「咳喘息」も増加しています。
当院では、これらの症状に基づき、適切な診断と治療を提供しています。
症状が出やすいタイミング
喘息発作は、夜間や早朝に起こりやすいという特徴があります。
タバコの煙、線香の煙、強い臭いなどを吸い込んだ時、風邪をひいた時、疲れている時、天候が悪い時、季節の変わり目、気温差が大きい時なども喘息発作が出やすくなります。
小児気管支喘息の原因
 小児気管支喘息は、主にアレルギー体質が関与していますが、その要因はさまざまです。
小児気管支喘息は、主にアレルギー体質が関与していますが、その要因はさまざまです。
小児喘息を患う多くのお子様は、ダニなどのハウスダストや花粉に対するアレルギーを合併しています。
これらのアレルゲンは喘息を悪化させる要因となります。
他にも、感染症、気圧変化、低温の空気、タバコ・花火・お香などの煙、ストレスなども喘息を悪化させる原因となります。
喘息治療では、発作の予防が重要です。
当院では、お子様一人ひとりの悪化要因を特定し、効果的な対策を指導しています。
アレルゲン
ダニ、カビ、ペットの毛やフケ、虫の死骸や糞、衣類の繊維、花粉などのアレルゲンを吸い込むと、気道に付着しアレルギー反応を引き起こします。
こまめな掃除でアレルゲンを減らし、清潔な環境を維持することが大切です。
当院では、血液検査などで一般的なアレルゲンを特定できます。
感染症による炎症
風邪の多くはウイルスによる上気道感染症であり、これが喘息発作の誘因となることがあります。
風邪をひいたと感じたら、喘息の症状が悪化する前に当院を受診し、早期治療に努めましょう。
運動
激しい運動により口呼吸になると、冷たい空気が気道に入り込み、運動誘発喘息と呼ばれる喘息発作を引き起こすことがあります。
短時間の軽い運動では発作が起きなくても、長時間の運動で発作が生じることもあります。
特に冬は、空気が冷たく乾燥しているため、運動誘発喘息が起こりやすい時期です。
運動誘発喘息の既往があっても、適切な対策を講じれば運動は可能です。
ただし、お子様ごとの状態に合わせた制限が必要となる場合があります。
当院では、発作予防のための治療や指導を行っています。
気候や温度
喘息発作は、気温や湿度の変化だけでなく、気圧の変化によっても誘発されることがあります。
冬季の室内から屋外の温度差、昼夜の寒暖差、低温で乾燥した環境、台風などによる急激な気圧変化が、発作の誘因となることがあります。
大気汚染物質
気管支喘息では、気管支粘膜に慢性的な炎症が生じ、過敏な状態になっています。
大気汚染物質(黄砂、PM2.5、花粉、花火・タバコ・お香などの煙)が刺激となり、喘息発作を引き起こすことがあります。
特に喘息のお子様がいるご家庭では、喫煙は厳禁です。
屋外で喫煙した場合も、呼気に有害物質が含まれている可能性があるため、しばらくの間、室内に入らないようにしてください。
ストレス・疲労など
疲労、寝不足、強いストレスによって大量に分泌されたストレスホルモンが、体内で炎症性物質を放出し、喘息発作を引き起こすことがあります。
発作時の対処法
発作時の症状
次のような症状が見られる場合は、喘息発作が重症化している可能性があります。
速やかに医療機関を受診してください。
- 唇の色が白い、または青紫色になっている
- 息を吸う時に小鼻が大きく動く
- 息を吸う時に胸がへこむ
- 横になれない、眠れない、歩けない
- 言葉を発することが困難、意識がもうろうとしている
- 異常に興奮する、暴れる
すぐに吸入薬
→場合によっては救急車を
ご家庭で急性発作が起きた場合は、緊急性が高い状態です。
すぐに処方されている発作時の吸入薬を使用し(20~30分ごとに最大3回まで吸入可能)、医療機関を受診してください。
呼吸困難が顕著であったり、意識レベルの低下や興奮状態が見られる場合には、救急車の要請をご検討ください。
特に2歳未満のお子様は症状の進行が速いため、迅速な対応が必要です。
喘鳴(「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音)がなくても、発作を起こしていることがあります。
お子様の顔色、動作、食欲、睡眠、会話の様子などに注意し、異変を感じたらすぐにご相談ください。
小児気管支喘息の治療と
長期管理
 喘息は慢性的な気道炎症が特徴です。
喘息は慢性的な気道炎症が特徴です。
炎症により傷ついた気道粘膜の修復には時間がかかり、一度傷ついた部分は刺激に過敏になり、発作を起こしやすくなります。
この状態が続くと肺機能の低下につながるため、当院では、健常なお子様と変わらない日常生活を送れるよう、喘息のコントロールを治療目標としています。
環境整備
喘息発作を予防するためには、生活環境から原因物質を減らすことが重要です。
主なアレルゲンは「ダニ」と「ハウスダスト」です。
こまめに掃除機をかけ、週1回は布団を干すことで、これらのアレルゲンをできるだけ除去しましょう。
ペット(犬、猫、鳥など)の飼育は控えることが望ましいです。
また、タバコの煙は小児の気道を刺激するため、ご家族の禁煙をお勧めします。
運動療法
喘息症状が落ち着いている時期には、適度な運動で基礎体力を向上させることが大切です。
発作の予防や重症化抑制に効果が期待できます。
水泳やウォーキングなどが推奨されますが、適切な治療を受けていれば、基本的にどのような運動でもよいので、お子様が楽しみながら続けられる運動を選びましょう。
ただし、運動によって喘息発作が誘発される「運動誘発喘息」には注意が必要です。
運動前のウォーミングアップや、乾燥した環境でのマスク着用で予防できます。
発作が多い場合は、運動前に気管支拡張薬を吸入または内服します。
発作時は、楽な姿勢でゆっくりと呼吸し、少しずつ水分を補給しながら安静にします。
気管支拡張薬があれば使用しましょう。
多くの場合、15分ほどで症状は治まりますが、改善しない場合は当院を受診してください。
運動のたびに発作が起こる場合は、喘息のコントロールが不十分な可能性があり、治療の見直しが必要です。
薬物療法
喘息の治療には、発作が起きた時に使用する薬と発作を予防する薬の2種類があります。
発作が起きた時に
使用する薬
気管支を拡げる薬として、飲み薬や吸入薬、貼付薬があります。息苦しい、ゼーゼーする、咳が続くなどの発作が出た時には、迷わず使用してください。
また、症状が強い時や長引く時には、ステロイドの飲み薬や注射薬を使用することがあります。
発作を
予防する薬
喘息のお子様の気管支には慢性的にアレルギー性の炎症があります。この炎症を抑え発作を起こさないようにするために、症状がなくても長期管理薬を継続することが重要です。
小児の気管支喘息の長期管理薬は、吸入ステロイド薬が中心です。
しかし、乳幼児では吸入手技が難しいため、シングレアやオノンなどのロイコトリエン受容体拮抗薬が第一選択となります。
治療薬は、発作の重症度、年齢、生活背景などを考慮して決定します。
治療はステップ1~4の4段階に分けられています。
乳幼児の軽症例では、ロイコトリエン受容体拮抗薬を主に使用しますが、発作頻度が多い場合やコントロールが不十分な場合は、吸入ステロイド薬を使用します。
学童以上では、軽症例でも吸入ステロイド薬の使用が推奨されます。
症状、検査結果、ピークフロー値が安定していれば、徐々に薬を減量(ステップダウン)していきます。
治療効果の確認とステップダウンを含めた見直しは、3~6か月ごとに行います。
小児気管支喘息は
何科を受診する?
お子様に喘息の疑いがある場合は、花粉症と同様に基本的に長く診てもらえる小児科・アレルギー科を受診するのが適切です。
当院でも、豊富な経験をもとに治療を行っておりますので、お気軽にご相談ください。