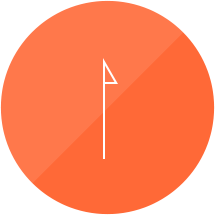子どものおっしっこが出ない
おしっこの回数や量は、年齢やその日の気温、汗の量などの環境によって変化し、個人差もあります。
当院では、お子様の全身状態を診る際に、体温や全身状態に加え、排尿・排便の回数も参考にします。
おしっこが出ない原因
 おしっこが出ない原因は、主に「おしっこを作れない」、「作ったおしっこを出せない」の2つが考えられます。
おしっこが出ない原因は、主に「おしっこを作れない」、「作ったおしっこを出せない」の2つが考えられます。
これらは超音波検査で膀胱内の尿の貯留を確認することで区別できます。
当院では、おしっこが出ないお子様に対し、必要に応じて超音波検査を行います。
おしっこを作れない
(無尿・乏尿)
発熱や嘔吐、下痢が続いて、全く水分が摂取できない状態では、体内の水分と電解質が不足します。
この場合、脱水状態となり、尿が作られなくなります
また、腎臓の機能が低下したり、蛋白質が尿中に漏れ出すことで、おしっこが作られなくなることもあります。
この場合は、水分を摂取していてもおしっこが出ず、むくみが現れます。多くの場合、おしっこが出ないことよりも、むくみに先に気付くことが多いです。
考えられる病気
- 脱水症(原因:嘔吐・下痢症、ウイルス性/細菌性腸炎、尿路感染症など)
- 急性糸球体腎炎(腎機能の低下)
- ネフローゼ症候群(高度蛋白尿による低蛋白血症)
作ったおしっこを出せない(尿閉)
水分は摂取できているのにトイレを我慢している、陰部を痛がるといった症状が見られる場合は、尿道炎、外陰炎、亀頭包皮炎など、尿の通り道や出口が感染している可能性があります。
また、外傷による尿道損傷や結石による尿路狭窄・閉塞も、尿が作られても排出できない原因となります。
さらに、お子様によっては学校や家庭でのストレスが影響して、排尿がうまくできなくなることもあります。
考えられる病気
- 尿道炎・外陰炎
- 尿道損傷
- 尿路結石
- 神経因性膀胱
- ストレス・心的要因
このような時は救急外来を受診しましょう
- 半日以上おむつが濡れていない(おしっこが出ていない)。
- 両まぶたが腫れ、顔や足など全身がむくんでいる。
- 唇や舌が乾き、眼球がくぼんでいる。(脱水症状)
- 下腹部(膀胱)が張って腹痛を訴えているのに、おしっこがでない。
- 痛みでぐったりしている。
- 何度も血尿が出る(ただし、元気で1回だけの血尿であれば、必ずしもすぐに受診する必要はありません)。
おしっこが出ない時の治療
治療は原因によって異なります。
おしっこを作れない
(無尿・乏尿)
脱水症の場合は、経口補水液や点滴で水分を補います。
腎機能の低下やネフローゼ症候群により尿量が減少している場合は、入院治療が必要となるため、専門の医療機関へご紹介いたします。
作ったおしっこを出せない(尿閉)
尿道炎や外陰炎、亀頭包皮炎には抗菌薬の内服や軟膏を使用します。
女の子の場合、おりものなどで陰部が汚れることがあるため、優しく洗ってあげてください。
男の子も、不衛生が原因のことが多いため、亀頭・包皮をぬるま湯で優しく洗ってあげてください。
尿道損傷や尿路結石の場合、特別な処置や手術が必要になることもあります。
神経因性膀胱に対しては、尿道カテーテルを用いた導尿や排尿訓練が有効な場合があります。
頻繁におしっこに行く
 子どもの排尿回数は年齢とともに変化し、成長するにつれて減少します。
子どもの排尿回数は年齢とともに変化し、成長するにつれて減少します。
4~5歳を過ぎても、1日の排尿回数が10回以上、または排尿間隔が2時間未満の場合は、頻尿の可能性があります。
| 年齢 | 排尿間隔 | 排尿回数の 目安 |
| 1~2歳 | 2時間おき | 8~12回 |
|---|---|---|
| 3~4歳 | 3時間おき | 5~9回 |
| 4歳以降 | 3~6時間おき | 4~8回 |
子どもの頻尿の原因
頻尿の主な原因は、尿量が多いこと(多尿)と、膀胱で尿を貯められないこと(膀胱機能の異常)、の2つに分けられます。
多尿の原因としては、尿崩症や糖尿病、腎尿路の異常などが挙げられます。
一方、膀胱機能の異常の原因には、尿路感染症、過活動膀胱、心理的要因(心因性頻尿)があります。
尿崩症
過剰な水分摂取も頻尿の原因となりますが、まれに尿崩症という病気によって多飲・多尿になることがあります。
尿崩症は、尿を濃縮するホルモンの作用不足により、尿量が増加し、強い喉の渇きから水を大量に飲むようになる病気です。
糖尿病
糖尿病は、血中から溢れたブドウ糖が尿中へ漏れ出す病気です。尿中にブドウ糖が漏れ出すことで、尿の浸透圧が高くなり、大量の尿が作られます(浸透圧利尿)。
多尿により水分が失われるため、喉の渇きが生じ、それに対して多飲という行動が認められます。
また、夜間の頻尿による覚醒などの症状も特徴的です。
尿路感染症(膀胱炎)
頻尿、残尿感、排尿時の痛み、下腹部の違和感、肉眼的血尿残尿感、トイレが近いなどの症状は、大腸菌などの細菌感染による膀胱炎でみられます。
尿検査で白血球や細菌を調べ、抗菌薬で治療します。
過活動膀胱
尿意がないのに膀胱が収縮し、「尿意を我慢できない」状態になることがあります。
これは、お子様の膀胱容量が小さく、膀胱や尿道の機能が未熟なことが原因である場合が多いです。
多くは成長とともに自然に改善しますが、頻繁な尿漏れが続く場合は、検査や治療が必要になることもあります。
心因性頻尿
心因性頻尿の特徴として、排尿しても尿量が少ない、睡眠中は排尿がない、遊びに集中しているときは尿意を感じない、などが挙げられます。
ストレスや緊張が原因と考えられており、トイレトレーニング開始直後によくみられる症状です。
多くの場合、一時的なものですが、頻尿が日常生活に支障をきたしたり、長引いたりする場合は、当院にご相談ください。
このような時は
受診しましょう
頻尿に加えて、発熱、腹痛、血尿、排尿痛、多飲などの症状がある場合は、当院を受診してください。
子どもの頻尿の治療
治療は原因によって異なります。
多尿を引き起こす尿崩症や糖尿病、腎尿路の異常に対しては、入院治療が必要となるため、専門の医療機関へご紹介いたします。
膀胱機能の異常の場合も、「尿路感染症」によるものか、「心因性」によるものかで治療法が異なります。
尿路感染症(膀胱炎)
膀胱炎の診断には尿検査を行い、尿中の白血球や亜硝酸塩の有無を確認します。
また、超音波検査で膀胱壁の肥厚や血流亢進の有無を評価します。
治療は抗菌薬の内服を行い、通常は数日で改善します。
膀胱炎が治癒すれば、頻尿も解消されます。
心因性頻尿
頻尿の原因となる出来事がある場合は、お子様の気持ちに寄り添い、安心できる環境を整えてあげることが大切です。
「またトイレに行くの?」などと指摘すると、かえって緊張を強めてしまうことがあります。
トイレの回数を気にしすぎず、お子様の気を紛わせながら、自然に落ち着くのを見守りましょう。
多くの場合、時間とともに症状が改善しますが、長引く場合は、膀胱の緊張を和らげ、過敏性を抑える薬を使用することがあります。