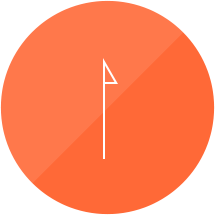食物アレルギーとは
 食物アレルギーは、乳幼児に多く、特定の食品(アレルゲン)の摂取によりアレルギー反応が引き起こされる疾患です。
食物アレルギーは、乳幼児に多く、特定の食品(アレルゲン)の摂取によりアレルギー反応が引き起こされる疾患です。
代表的なアレルゲンには、卵、牛乳・チーズ・バターなどの乳製品、米、大豆、小麦粉、そば、エビ・カニ等の甲殻類、ピーナッツ・カシューナッツなどのナッツ類、果物などがあります。
また、今まで問題なく摂取できていた食品でも、突然アレルギー反応を起こすことがあります。
アレルギー症状は、咳や喘鳴(ヒューヒューという呼吸音)などの呼吸器症状、じんま疹などの皮膚症状、嘔吐・下痢・腹痛といった消化器症状、そしてアナフィラキシーショックなど、多岐にわたります。
特にアナフィラキシーショックは生命に関わるため注意が必要です。
当院でアドレナリン自己注射薬(エピペン)を処方されているお子様は、症状が現れたら速やかに使用ください。
治療の基本第一は、アレルゲンとなる食品の除去です。
原因が特定できていない場合は、アレルギー検査で行います。
対症療法として、皮膚症状にはステロイド外用薬、かゆみには抗アレルギー薬を使用します。
食物アレルギーの
分類と症状・原因
食物アレルギーは、発症メカニズムや症状の現れ方によっていくつかのタイプに分類されます。
主な分類について、以下に説明します。
新生児・乳児消化管
アレルギー
新生児や乳児に起こる消化管アレルギー疾患で、ミルクや母乳をはじめとする食品が原因となります。
母乳の場合、お母様の食事が影響することもあります。
症状は様々ですが、
主な症状
原因となる食品を摂取後、数時間から数日後に下痢、血便、嘔吐などの消化器症状が現れ、体重増加不良の原因となることもあります。
多くの場合、原因となる食品を除去することで改善しますが、長期的な管理が必要となるケースもあります。
食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、環境要因と遺伝的素因が関与して発症しますが、乳幼児期では食物アレルギーが原因となる場合があります。
主な症状
乳児期では、卵、牛乳、大豆などがアレルゲンとなり、湿疹や皮膚の乾燥などの症状が現れます。
これが慢性化すると、アトピー性皮膚炎に進行することがあります。
多くの場合、成長と共に症状は改善しますが、適切な食事管理とスキンケアを継続することが重要です。
即時型食物アレルギー
食物アレルギーの中で最も一般的な即時型では、原因となる食品の摂取後、主に2時間以内に症状が現れます。
多くの場合、30分~60分以内にピークを迎え、重症でなければ半日程度で症状が軽快します。
食物アレルギーでは遅延型や遅発型などもあり、症状が出るタイミングは様々です。
主な症状
皮膚症状(かゆみ、赤み、蕁麻疹、湿疹など)が最も現れやすく、呼吸器症状(喘鳴、咳、息苦しさ)や消化管症状(嘔吐、下痢、腹痛)など多岐にわたります。
食物依存性運動誘発
アナフィラキシー
学童期以降に多い、比較的まれな食物アレルギーで、特定の食物を摂取したに運動をすると、アナフィラキシー反応が誘発されます。
また、運動以外にも月経前症状、ストレス、風邪、寝不足、疲労、アスピリン服用、気象条件などが誘因となることがあります。
主な症状
呼吸困難、せき込み、顔面や手足のむくみ、全身の蕁麻疹などが現れ、症状は急速に進行します。
約半数のお子様は血圧低下によるショック症状を起こすため、発症時は速やかに救急車を呼び、医療機関へ搬送することが重要です。
口腔アレルギー症候群(OAS)
果物や野菜を摂取した後に、口や喉のかゆみ、喉の奥の詰まり感などを生じるアレルギー反応です。
これは、花粉症と関連して発症することが多く、特定の花粉と果物・野菜に含まれるタンパク質が交差反応を起こすこと原因です。
例えば、シラカバ花粉症のお子様がリンゴを食べた際に発症することがあります。
通常は軽症ですが、まれに重篤な反応を起こすため注意が必要です。
主な症状
果物や野菜の摂取により、口や喉のかゆみ、喉の奥の詰まり感、まれに重篤なアナフィラキシー反応を生じます。
症状が強い場合は、速やかに医療機関を受診してください。
食物アレルギー一覧
表示が義務付けられているアレルギー物質
 【特定原材料8品目】
【特定原材料8品目】
- 卵
- 乳(牛乳)
- 小麦
- えび
- かに
- くるみ
- 落花生(ピーナッツ)
- そば
表示が推奨されている
アレルギー物質
【特定原材料に準ずるもの20品目】
- アーモンド
- あわび
- いか
- いくら
- オレンジ
- カシューナッツ
- キウイフルーツ
- 牛肉
- ごま
- さけ
- さば
- 大豆
- 鶏肉
- バナナ
- 豚肉
- マカダミアナッツ
- もも
- やまいも
- りんご
- ゼラチン
食物アレルギーの検査
食物アレルギーの診断には、「どの食品」を「どのような状況」で摂取した際に「どのような症状が現れるか」を正確に把握することが重要です。
当院ではまず問診を行い、摂取した食品の種類や量、症状が現れるまでの時間、症状の持続時間など、発症の経緯を詳しくお伺いします。
そのうえで、原因となる可能性ある食品や重症度を考慮し、適切な検査方法を検討します。
食物負荷試験
食物負荷試験とは
食物アレルギーの疑いがある食品、またはアレルギーが確定している食品を、医療機関において医師の厳重な管理のもとで実際に摂取していただき、アレルギー症状が現れるかどうか、また安全に食べられる量を診断する検査です。
対象者
再診の患者様が対象です。
当日持参品
- 負荷する食品(指示されたもの)
- 頓服薬
- スプーンや箸など
※ゆで卵は20分茹でた固ゆでのものを持参してください
※たまこなを負荷する場合は、当院で用意をしています。
ふりかけのような製品のため、一緒に食べられるものを持参してください。
注意事項
- 食物負荷後、1時間程度は院内でアレルギー症状の出現がないかを観察します。
時間に余裕をもってお越しください。 - 体調が悪いとき、喘息発作がでているようなとき、直近でアレルギー症状が出たときなどは、負荷試験が行えませんので、予約のキャンセルもしくは変更をお願いします。
特異的IgE抗体検査
(血液検査)
血液中のIgE抗体の量を測定し、特定の食物のアレルゲンに対するアレルギーの可能性を評価する検査です。
食物アレルゲンに対するIgE抗体は抗原の種類によって異なり、特定のIgE抗体の値が高い場合、対応する食物へのアレルギーの可能性が高くなります。
ただし、IgE抗体の値が高くても症状が出ない場合があり、この検査結果のみで食物アレルギーの確定診断を行うことはできません。
プリックテスト
(皮膚テスト)
乳幼児や口腔アレルギー症候群のお子様に有効なプリックテストでは、アレルゲンになりうる物質の液体を皮膚に滴下し、針で軽く刺して皮膚の反応(腫脹、発赤など)を観察します。
赤く腫れた場合、その物質を含む食物にアレルギー反応を示す可能性が高いと判断されます。
食物除去試験(除去試験)
血液検査や皮膚テストで原因として疑われる食物を一定期間(1~2週間)完全に除去し、湿疹などの症状の改善を確認する方法です。
除去によって症状が改善した場合、その食物がアレルゲンである可能性が高いと判断されます。
乳児のアトピー性皮膚炎で、治療にもかかわらず症状が改善しない、または悪化している場合、食物アレルギーを併発している可能性があります。
食物アレルギーに対する治療
当院では、食物アレルギー診療ガイドライン2021に従って、「必要最小限の、正しい診断に基づいた除去」を方針としています。
現時点で通常量を摂取できなくても、少量から継続的に摂取することで、将来的に食物アレルギーを克服できる可能性があります。
食事指導
(必要最小限の除去)
 かつては、アレルギー検査で陽性反応が出た食品を全て除去するように指導されることが一般的でしたが、この方法が食物アレルギーのお子様の増加につながったことが明らかになっています。
かつては、アレルギー検査で陽性反応が出た食品を全て除去するように指導されることが一般的でしたが、この方法が食物アレルギーのお子様の増加につながったことが明らかになっています。
実際に食物アレルギーのあるお子様でも、全く食べられないケースは少なく、微量でも継続的に摂取することで、体がその食品を異物と認識しなくなり、閾値が上昇することで寛解に至る可能性があります。
スキンケア
皮膚の乾燥や湿疹を放置すると、皮膚のバリア機能が低下し、そこからアレルゲンが侵入してIgE抗体が作られる「経皮感作」が起こります。
経皮感作は食物アレルギーだけでなく、さまざまなアレルギー疾患の発症リスクを高めます。
湿疹を早期に治療し、スキンケアを徹底することが、食物アレルギーの予防につながるということが研究で明らかになっています。
食物アレルギーが現れた時の
対処法
症状の持続時間
軽度のアレルギー反応であれば、通常数時間以内に症状は治まります。
しかし、アナフィラキシーショックなどの重篤な症状が現れた場合、数日間症状が続くこともあり、入院が必要となることもあります。
【緊急時】重症・アナフィラキシーショックの時
以下のような症状がみられた場合は、直ちに適切な対応をとる必要があります。
- 意識がもうろうとする
- ぐったりする
- 呼吸困難
- 持続する激しい腹痛
- 繰り返す嘔吐など、全身状態が悪い
- アドレナリン自己注射薬(エピペン®)を所持している場合は、直ちに使用してください。
- 救急車を呼びましょう。
- 症状に応じた安静姿勢をとらせます。
意識障害やぐったりしている場合は、血圧低下の可能性があるため、足を高くして仰向けに寝かせます。
呼吸困難で仰向けになれない場合は、上体を起こして背中に支えを入れます。
吐き気がある場合は、吐物による窒息を防ぐため、体と顔を横向きにします。 - 救急車を待つ間に呼吸停止した場合、心肺蘇生を行います。
こんな時は要注意!
 以下のような症状がみられた場合も、速やかに医療機関を受診してください。
以下のような症状がみられた場合も、速やかに医療機関を受診してください。
- 軽い咳
- 腹痛
- 1~2回の嘔吐・下痢
- 顔やまぶたの腫れ
- 皮膚の強いかゆみや赤み
- 蕁麻疹
- 内服薬を飲ませる
- 医療機関を受診する(状況に応じて救急車を要請)
- 受診まで5分おきに症状をチェックし、重症化していればエビペン®を使用する
「水を飲む」のは
効果があるの?
残念ながら、水を飲むことによるアレルギー症状の予防や軽減効果はありません。
発症予防には、適切な時期に離乳食を開始することや、皮膚の炎症を早期に治療することが有効とされています。