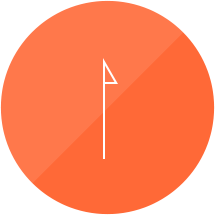おたふくかぜ
(流行性耳下腺炎)とは?
 「おたふくかぜ」とも呼ばれる流行性耳下腺炎は、ムンプスウイルスによって引き起こされる感染症で、耳の下(耳下腺)が腫れるのが特徴です。
「おたふくかぜ」とも呼ばれる流行性耳下腺炎は、ムンプスウイルスによって引き起こされる感染症で、耳の下(耳下腺)が腫れるのが特徴です。
主に3~6歳のお子様が罹患しますが、大人を含め、あらゆる年齢で感染する可能性があります。
おたふくかぜの症状
潜伏期間は2~3週間で、その後、片側または両側の唾液腺、特に耳下腺(耳の下)の腫脹を伴って発症します。
多くの場合、片側の痛みから始まり、1~2日後にもう片方も腫れますが、約4分の1のケースでは片側のみで治まります。
腫れは1~3日でピークに達し、3~7日で軽快します。
症状として、微熱、頭痛、倦怠感を伴うことが多く、高熱になる場合もあります。
また、合併症として、まれに難聴(永続的)、思春期以降では精巣炎や卵巣炎、髄膜炎や膵炎などを発症することがあります。
おたふくかぜと似た症状を示す疾患として、他のウイルス性耳下腺炎や反復性耳下腺炎があり、後者は発熱を伴わないことが多いのが特徴です。
合併症
合併症として、無菌性髄膜炎(1~10%)、男性では精巣炎(25%)、女性では卵巣炎(5%)などを発症します。
また、まれですが、約1000人に1人の割合でムンプス難聴という重篤な合併症を発症し、片側(まれに両側)の難治性聴覚障害を引き起こします。
有効な治療法がないため、ワクチン接種による予防が推奨されます。
おたふくかぜか普通の風邪か見分けるには
おたふくかぜと風邪の大きな違いは、耳の下にある「耳下腺」の腫れです。
ムンプスウイルスに感染すると耳下腺に炎症が起こり、特徴的な「おたふく」様の腫れが現れます。
この腫れは2日程度でピークに達し、1週間ほどで消失します。
また、38度を超える発熱、頭痛、咳、咽頭痛などの症状も現れ、こちらも約2日でピークを達します。
耳下腺の腫れが引いた後も、これらの症状が続くことがありますが、概ね1週間で回復します。
おたふくかぜの原因
流行性耳下腺炎はムンプスウイルスによる感染症で、潜伏期間は2~3週間です。
一度感染すると生涯免疫を獲得するとされていますが、まれに再感染することもあります。
感染経路
感染経路は、咳やくしゃみによる飛沫感染と、ウイルスが付着した手で口や鼻を触る接触感染です。
発症2日前から耳下腺の腫れが消退するまで感染力が持続します。
おたふくかぜの治療方法
 ムンプスウイルスに対する特効薬はないため、治療は対症療法が中心となります。
ムンプスウイルスに対する特効薬はないため、治療は対症療法が中心となります。
発熱には解熱鎮痛剤を使用し、脱水予防のために経口補水療法(水と電解質を口から補給する治療)を行います。必要に応じて点滴治療を行うこともあります。
おたふくかぜのワクチン・
予防接種について
 ムンプスウイルスワクチンは日本では任意接種ですが、世界的には定期接種としている国も多く、1回の接種で発症率を88%、2回の接種で99%減少させるというデータがあります。
ムンプスウイルスワクチンは日本では任意接種ですが、世界的には定期接種としている国も多く、1回の接種で発症率を88%、2回の接種で99%減少させるというデータがあります。
一般的に、1歳以降のなるべく早い時期に1回目を接種し、小学校入学前に2回目を接種するのが推奨されています。
ワクチン接種は、おたふくかぜの発症と合併症リスクを低減する重要な手段です。
予防接種したのに感染することはある?
ワクチン接種後も約10%のお子様は免疫を獲得できず、感染の可能性が残ります。
しかし、未接種の場合と比べて、発熱や耳下腺の腫れは軽度で、無菌性髄膜炎の発症率も低い傾向にあります。
合併症予防の観点からも、ワクチン接種は有効です。
子どものおたふくかぜは
大人にも感染する?
流行性耳下腺炎は大人にも感染することがあり、大人のほうが重症化しやすいとされています。
子どもの頃に感染したか不明な場合は、大人でもワクチン接種が推奨されます。
なお、すでに感染した経験のある方がワクチンを接種しても問題ありません。