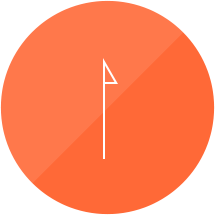すぐに受診が必要な熱の症状

次のような場合は、発熱の程度にかかわらず、速やかに医療機関を受診してください。
- ぐったりしている、または強い不機嫌
- 水分が摂れない
- 嘔吐を繰り返す
- 意識がはっきりしない
- 反応が鈍い
- なかなか寝付けない
また、生後3か月未満の乳児(特にワクチン接種をしていない場合)は、発熱があれば必ず早めに受診しましょう。
そもそも、なぜ熱が出るの?

お子様の発熱は、ウイルスや細菌と戦うための体の防御反応です。
体温が上がることで免疫細胞の活動が活発になり、ウイルスや細菌への攻撃力が高まります。
つまり、発熱は身体にとって大切な防御反応です。
お子様が元気であれば、必ずしも解熱剤の使用や受診を急ぐ必要はありません。
発熱時にぐったりしているのは、体が休息を必要としているためと考えられます。
解熱剤は単に「熱を下げる」ためのものではなく、「つらさを和らげる」ために使うこともできます。
使用する際には熱だけでなく、お子様の様子を見て判断しましょう。
子どもの発熱の原因となる病気
突発性発疹
突発性発疹は、生後6か月~2歳頃の乳幼児に多く見られる発疹性の疾患です。
高熱が3日間ほど続き、解熱後に全身に発疹が現れます。
他の症状としては、機嫌が悪くなったり、食欲が落ちたりすることがありますが、特別な治療法はなく、自然に治る病気です。
ただし、高熱により熱性けいれんを合併することがあります。
麻疹(はしか)
麻疹は、非常に感染力が強い麻疹ウイルスによる感染症です。
発熱、咳、鼻水、目やになどの症状が2~3日続き、一旦解熱した後、再び高熱が出て、全身に発疹が現れます。初期症状だけでは、重度の風邪と区別が難しい感染症です。
肺炎、中耳炎、脳炎などの合併症を引き起こす可能性があり、重症化すると、死に至ることもあります。
しかし、予防接種を2回行うことで、ほぼ確実に免疫を獲得できますので、1歳と小学校入学前の2回のワクチン接種を受けてください。
水痘(水ぼうそう)
水痘は、水痘・帯状疱疹ウイルスによる感染症で、全身に水ぶくれ状の発疹(水疱)が現れる疾患です。
軽症の場合は発疹も少なく、熱が出ないこともあります。
重症化すると、高熱が続き、全身に多数の発疹が現れます。
乳児や基礎疾患のあるお子様など、免疫が低下している方は重症化することがあるため注意が必要です。
発疹(水疱)がかさぶたになる(痂皮化する)まで感染力があるため、登園・登校は控えて下さい。
水痘ワクチンが最も有効な予防法です。ワクチン接種で発症を予防し、発症しても重症化を防ぎ、症状が軽く済むことが多いです。1歳になったらぜひ予防接種を受けてください。
アデノウイルス
アデノウイルスは、プール熱(咽頭結膜熱)や流行性角結膜炎の原因ウイルスです。
プール熱はのどが赤く腫れ、高熱が4~5日続きます。
目の充血(結膜炎)、頭痛、吐き気、下痢、高熱による倦怠感などの症状を伴うこともあります。
プール熱は夏に多く見られますが、1年を通して感染する可能性があります。
重症化すると肺炎を合併することもあります。
流行性角結膜炎は強い目の充血、まぶたの腫れ、目やに涙が止まらないなどの症状を引き起こします。
非常に感染力が強く、学校や保育園では「第二種感染症」に分類され、医師の許可が出るまで登園・登校ができません。
目の症状が出た場合はタオルの共用を避け、手洗いを徹底しましょう。
家族内感染にも注意が必要です。
ヘルパンギーナ
ヘルパンギーナは、エンテロウイルスやコクサッキーウイルスにより引き起こされる夏風邪の一種です。
高熱、のどの赤み・痛み、水疱(水ぶくれ)などの症状が現れます。
発熱は2~3日で解熱しますが、のどの痛みがひどく食事・水分摂取が困難になることもあります。
まれに重症化し、高熱による「熱性けいれん」や「脱水症状」を起こすことがあります。
ぐったりしている場合や脱水兆候がある場合は、早めに受診しましょう。
溶連菌感染症
溶連菌感染症は、溶連菌による感染症で、発熱、のどの痛み、発疹などの症状が現れます。
のどは赤く腫れ、白い膿点(白苔)が付着し、舌はイチゴのように赤くザラザラになることがあります。
感染力が強いため、発症した場合は学校や保育園は医師の許可が出るまで出席停止となります。
抗菌薬の種類によって治療期間は多少異なりますが、7-10日間の抗菌薬治療が必要です。
合併症として急性糸球体腎炎を起こすことがあるため、感染後2~3週間経過したら尿検査を受けることをお勧めします。
RSウイルス感染症
RSウイルスは、気道感染の原因となるウイルスの一つです。
保育所などでの集団感染のリスクが高く、毎年感染する可能性があります。
年長児や成人は軽症の風邪で済むことが多いですが、乳児、特に6か月未満の乳児では重症化しやすく、呼吸障害や哺乳不良などの症状が現れ、入院加療が必要となる場合もあります。
呼吸が速く、苦しそう、ミルクや母乳が飲めない、ぐったりしている、顔色が悪い(青白い唇)などの症状がある場合は、すぐに受診してください。
また、喘息を持つお子様も、RSウイルス感染により喘息発作を起こす可能性があるため、流行期には特に注意が必要です。
インフルエンザ
インフルエンザは、毎年冬に流行する感染症です。
発熱、咳、鼻水、のどの痛み、腹痛、下痢など、風邪に似た症状が現れますが、風邪よりも症状が重く、高熱や倦怠感などの全身症状が強く出るのが特徴です。解熱まで1週間程度かかることもあります。
肺炎や脳炎などの合併症のリスクもあるため、注意が必要です。
インフルエンザウイルスにはA型とB型があり、迅速診断キットで早期診断が可能です。
発症48時間以内であれば、抗ウイルス薬による治療が有効な場合があります。
感染力が非常に強く、幼稚園、学校、職場など人が集まる場所で感染しやすいです。
帰宅後の手洗いうがい、予防接種で感染と重症化のリスクを低減しましょう。
流行前(10~12月)にワクチンを接種することが、感染予防と重症化の予防に効果的です。
おたふくかぜ
(流行性耳下腺炎)
おたふくかぜは、耳下腺にムンプスウイルスが感染することで、耳の下が腫れるウイルス感染症です。
片側または両側の耳下腺が腫れ、痛みや発熱を伴うこともあります。
髄膜炎を合併するリスクがあり、頭痛や嘔吐がある場合は特に注意が必要です。
稀に、膵炎や精巣炎を合併し、難聴の後遺症を残すこともあります。
予防接種は任意ですが、接種をお勧めします。
川崎病
川崎病は、乳幼児に好発する原因不明の発熱をきたす病気です。
主な症状は、長期にわたる高熱、発疹、眼球結膜の充血、手足の腫脹、リンパ節の腫れ、口唇や舌の発赤などが特徴です。
全身の血管に炎症が起こり、心臓の血管に炎症が及ぶと冠動脈瘤を合併する可能性があります。
早期発見・早期治療により治癒が期待できますが、1~3週間の入院治療が必要となります。
熱が出やすい・繰り返すのは
大丈夫?
感染経験のない子どもが
熱を出しやすいのは
自然なこと
 発熱は、小児期に非常に多くみられる症状で、当院でも受診理由の上位を占めています。
発熱は、小児期に非常に多くみられる症状で、当院でも受診理由の上位を占めています。
特に生後6か月から1~2歳頃までのお子様は、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱いため、頻繁に発熱することがあります。
保育園・幼稚園に通い
始める時期は熱が出やすい
お子様が集団生活を始めると、さまざまな病原体に接触する機会が増えるため、特に保育園や幼稚園への入園初期は、発熱を繰り返すことがよくあります。
2-3年かけて徐々に免疫がついてくると、発熱の頻度は減少します。
乳幼児期は、中耳炎、気管支炎、肺炎などの感染症にかかりやすいため、必要に応じて当院を受診し、適切な治療を受けてください。
お子様の場合、夜間に発熱しても翌朝には解熱していることがありますが、夕方に再び発熱することもあります。そのため、夜間に発熱した場合は、翌朝解熱していても、安静にして様子を観察し、再発熱した場合は受診を検討してください。
24時間以上平熱が続いていれば、登園・登校が可能です。
子どもの発熱時に
気を付けること
こまめに水分補給をさせる
お子様は、大人に比べて体内の水分量が多く、体表面積も大きいため、高熱によって脱水症を引き起こしやすくなっています。
不機嫌や嘔吐で水分摂取ができない場合は、脱水症状に注意し、早めに当院を受診してください。
授乳中であれば母乳やミルク、離乳食後はイオン飲料、麦茶、湯冷ましなどをこまめに与えてください。
イオン飲料が理想的ですが、飲んでくれるならお茶や白湯でも構いません。
温度管理を行う
発熱初期には悪寒があるため、保温が必要ですが、手足や顔が赤くなってきたら、熱がこもらないように、厚着や布団の掛けすぎを避け、汗をかいたらこまめに着替えをさせましょう。
首や脇、鼠径部などを冷やすのも効果的ですが、お子様が嫌がる場合は無理に行う必要はありません。
解熱剤はお子様の様子を見て使いましょう
お子様が元気で水分が摂れている場合は、解熱剤の使用は必ずしも必要ではありません。
しかし、痛みや倦怠感が強く、水分摂取や睡眠が十分に取れない場合は、解熱剤を使用して楽にしてあげましょう。解熱剤を使用する際には熱だけでなく、お子様の様子を見て判断してください。
当院では、アセトアミノフェンを解熱剤として処方することが多く、内服後30分ほどで効果が現れ、約4時間持続します。
解熱後は、こまめな水分補給と安静を心がけてください。
発熱に加えて、咳がひどい場合や呼吸が苦しい場合は、酸素消費量を減らすために解熱剤を使用します。
3日以上発熱が続く場合は、水分が摂れて元気な場合でも、受診をお勧めします。