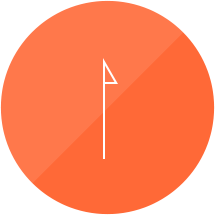子どものおねしょは何歳まで?
夜尿症とは何歳から?
 2~3歳頃までのお子様の「おねしょ」は、排尿機能が未熟なために生じる生理的な現象です。
2~3歳頃までのお子様の「おねしょ」は、排尿機能が未熟なために生じる生理的な現象です。
一方で、5歳以上のお子様が月に1回以上の頻度で睡眠中にお尿を漏らす状態が3か月以上続く場合、「夜尿症」と診断されます。
夜尿症の原因はさまざまで、病気のサインである場合もありますが、生活習慣や睡眠の改善で治ることもあります。
当院は腎臓専門医・指導医である院長が診察を担当します。
ご心配な場合は、お気軽にご相談ください。
夜尿症がある子どもの割合
夜尿症は男の子に多くみられ、5歳児では5~7人に1人、7歳児では10人に1人の割合で発症します。
多くの場合、年齢とともに自然に治癒し、思春期頃にはほとんどなくなります。
ただし、成人後も夜尿症が続く人が1%程度存在します。
夜尿症の原因
夜尿症の主な原因は、①睡眠中の尿量が多いこと、②睡眠中の膀胱容量が小さいことの2つです。
- 通常、夜間は「抗利尿ホルモン(バソプレシン)」が分泌され、尿量が減少しますが、このホルモンの分泌が未発達な場合、夜間の尿量が多くなります。
- 膀胱の容量が小さいと、夜間に十分な尿をためることができず、夜尿を引き起こしやすくなります。
その他にも、睡眠の深さ(尿意を感じても目が覚めにくい)、発達の遅れ、生活習慣(夕方以降の水分量が多い)、心理的要因(ストレスや環境の変化)が影響することがあります。
両親に夜尿症の既往がある場合、お子様も夜尿症になる確率は75%と高く、遺伝的要因も考えられます。
さらに便秘症があると膀胱が圧迫されて尿をためにくくなるため、夜尿症の原因として非常に重要です。
夜尿症のお子様の特徴
夜尿症のお子様は、一般的に眠りが深く、尿意で目覚めにくい傾向があります。
そのため、夜尿をしても気づかないことが多いです。
夜尿症の原因となりうる
注意すべき病気
夜尿症の原因として、尿量が多くなる内分泌疾患や腎臓・尿路の生まれつきの異常、膀胱の容量が小さくなる脊椎の病気、その他にもてんかんや睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れている場合があります。
そのような病気は、過去に夜尿が6か月以上なかった期間があるお子様で多く認められます。
その他にも昼間のお漏らし(尿失禁)や便漏れ(便失禁)がある場合も注意が必要です。
当院では、夜尿症の診察時にこれらの基礎疾患の有無を確認し、必要に応じて専門の医療機関へご紹介いたします。
腎臓・尿路の病気
夜尿症のお子様の中には、まれに腎臓・尿路の生まれつきの異常や膀胱の病気が見つかる場合があります。
生まれつき腎臓が小さかったり(低形成腎・異形成腎)、尿路が拡大している(水腎症)場合は、尿量が多くなるため、夜尿症を引き起こすことがあります。
また慢性膀胱炎や排尿筋過活動がある場合は、膀胱の容量が小さくなります。
当院では、問診でそれらが疑わしい場合は、血液検査や尿検査、超音波検査を実施いたします。
神経・脊椎の病気
小児の脊椎障害で最も多いのは、二分脊椎という生まれつきの脊髄の病気です。
二分脊椎の場合、膀胱内にうまく尿を貯めることができないため、夜尿症の原因となります。
また、てんかんが原因で夜尿症を生じることがあります。
内分泌の病気
夜間の尿量を抑える抗利尿ホルモンの分泌が低下する尿崩症や糖尿病では、尿量が増加し、夜尿症を引き起こすことがあります。
血液検査や尿検査により発見することができます。
喉・鼻の病気
アレルギーやアデノイド肥大は睡眠時無呼吸症候群の原因となり、睡眠リズムの乱れや夜間の低酸素血症を引き起こし、夜尿症の原因となることがあります。
当院では、必要に応じて耳鼻咽喉科での治療をお勧めすることもあります。
発達障害
自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)など発達障害のあるお子様では、健常なお子様よりも夜尿症が多くみられることが報告されています。
排尿コントロールの未熟さ、睡眠の質の問題(深すぎる睡眠や不安定な睡眠)、生活習慣の影響(水分摂取の偏りなど)、感覚過敏・鈍麻などが関与していると考えられています。
そのようなお子様には薬物治療だけでなく、お子様にあった生活習慣の工夫などを組み合わせて治療することが重要です。
夜尿症の治し方
原則は「起こさない・
怒らない・焦らない・
比べない」
 夜尿症は、育て方や性格とは関係がありません。
夜尿症は、育て方や性格とは関係がありません。
焦って叱ったり、無理に起こしたりすることは、治療の妨げとなるため避けましょう。
お子様を責めたり、自分を責めたりせず、夜尿症はよくある症状だと理解することが大切です。
「起こさない・怒らない・焦らない・比べない」を治療の原則として、お子様の良いところを積極的に褒めてあげましょう。
何よりお子様自身が「治したい」という気持ちを持つことが重要です。
焦らずに見守り、お子様の気持ちを尊重しましょう。
生活習慣の改善・経過観察
就寝・起床時間、食事内容、水分摂取、便秘、冷え性などの生活習慣を改善することにより、2~3割のお子様で夜尿症の改善が見られます。
生活習慣の改善は夜尿症治療の基本であり、薬物療法を行う場合も継続することが重要です。
生活・食習慣
 夜尿症の改善には、規則正しい生活習慣が大切です。
夜尿症の改善には、規則正しい生活習慣が大切です。
朝食と昼食はしっかり摂り、夕食は就寝3時間前までに済ませましょう。
水分の摂取は、午前中は多めにし、夕食後から就寝まではコップ1杯程度にしましょう。
食事内容は塩分を控え、薄味を心がけるようにしてください。
また夕食以降は牛乳やジュース、カフェインを含む飲料の摂取を控えましょう。
便秘は膀胱を圧迫し、夜尿症を悪化させるため、食物繊維を多く摂り便秘を予防しましょう。
トイレ
就寝前には、尿意の有無に関わらず、必ずトイレに行く習慣をつけましょう。
就寝時の注意
就寝時は、寝冷えしないように室温を適切に調整しましょう。
布団の掛けすぎは、寝冷えの原因となるため注意が必要です。
就寝中、無理に起こしてトイレに行かせることは避けましょう。
夜間排尿の習慣がつき、抗利尿ホルモンの分泌にも悪影響を及ぼすことがあります。
薬物療法
抗利尿ホルモン薬
(ミニリンメルト)
夜間の尿量を減らす効果のある薬で、夜間尿量が多いお子様に効果的です。
舌の下に置いて溶かし、水なしで服用します。水と一緒に服用すると効果が弱まります。
正しく服用しないと副作用のリスクが高まるため、服用時にはいくつかの注意点があります。
服用前後に水分を摂りすぎると水中毒を起こす危険があるため、服用2時間前から飲水を最小限に控え、服用後も過剰な水分摂取は避けてください。
また食事やおやつの摂取により効果が弱まるため、夕食後1時間以上あけてから服用し、服用後の飲食は避けてください。
当院では、夜尿症のお子様に対して服用上の注意点を十分に説明した上で処方しています。
抗コリン薬
膀胱の緊張を和らげ、尿をためやすくする薬で、膀胱容量の小さいお子様に効果的です。
即効性はなく、一定期間継続することが重要です(1~2か月後に効果を評価)。
ミニリンメルトと併用することが多いです。
副作用として、口の渇き、顔のほてりの他、便秘や眼圧上昇があるため、便秘症や緑内障のあるお子様には使用できません。
また尿が出にくくなったり、めまいや眠気が生じることもあります。
三環系抗うつ薬
抗利尿ホルモン薬や抗コリン薬で効果がない場合、補助的に使用される薬です。
便秘症に対する薬物治療
便が慢性的に貯留すると、膀胱が圧迫されることで夜尿症を引き起こします。
夜尿症の治療を行っても改善しない場合、便秘症を解消することで夜尿症が改善することがあります。
夜尿症治療の前に便秘症の治療を徹底することで、夜尿症が改善することもあります。
当院では、夜尿症で悩むお子様に対し、必ず便秘症の評価を行い、夜尿症の治療をスムーズに進めるためにも、まずは便秘症の解消に取り組みます。
便秘症に対する薬物治療には、便を柔らかくする浸透圧性下剤(モビコールや酸化マグネシウム)、腸蠕動を促す刺激性下剤(ピコスルファート)、漢方薬などを使用し、お子様に合った治療を行います。
アラーム療法
夜尿時にアラームが鳴るセンサー付きパンツを使用することで、夜尿後すぐにアラームで知らせて本人に認識させることで、睡眠中に尿意を感じて起きられるようになることを目的としています。
それを繰り返すことにより夜間睡眠中の膀胱容量が増える、夜間尿量が減る、といった効果が現れ、夜尿症の改善につながります。特に膀胱容量の小さいお子様に効果的です。
有効率は約70%とされ、効果が認められた場合、再発率が低く、副作用がないことがメリットです。
ただし、継続には保護者のサポートと、お子様の治療への意欲が不可欠です。
また、旅行などの際は、薬物療法と併用することも可能です。
診療の流れ
1初診:しっかりとお話を伺い、原因を調べます
まずはじっくりとカウンセリングを行い、お子様の生活リズムや排尿・排便の状況を確認します。
- 問診・生活指導
夕食の時間、水分の取り方、就寝前排尿の有無など、生活習慣の改善アドバイスを行います。
実は、生活習慣を見直すだけで改善するケースも少なくありません。 - 尿検査
尿の濃さや、タンパク尿、尿糖、炎症がないかを調べます。 - 超音波(エコー)検査
腎臓や膀胱の形、尿がしっかり出し切れているか(残尿がないか)、また便秘の有無などを、痛みのない検査で確認します。 - 治療方針の決定に必要なこと
夜尿症のタイプ(多尿型/膀胱型)を分類するため、夜間尿量やがまん尿量を自宅で測定いただきます。詳細は診察時に説明します
2再診以降:オンライン診療での継続も可能です
夜尿症のタイプ(多尿型/膀胱型)をもとに治療方針を決定します。
夜尿症の治療は、数ヶ月〜年単位でじっくり取り組むことが大切です。
当院では通院の負担を減らすため、2回目以降はオンライン診療にも対応しています。
-
- 遠方にお住まいの方も安心
ご自宅からスマートフォンで受診できるため、遠方からお越しの方や、学校・習い事で忙しいお子様でも継続しやすい体制を整えています。 - 経過観察
生活指導の効果や、お薬の調整を丁寧に行っていきます。
- 遠方にお住まいの方も安心
子どもの夜尿症は
何科を受診する?
小学校入学後も夜尿が続く場合は、小児科への受診をお勧めします。
海外研究によると、夜尿症のお子様は自尊心が低い傾向があり、治療によって症状が改善すると自尊心の回復が見られると報告されています。
夜尿症は、お子様の性格や親の育て方が原因ではありません。
よくあるご質問
病院へ行く目安はありますか?
小学校入学後も夜尿が続く場合は、ご相談ください。
また、入学前でも5歳以降のお子様で「夜尿症を治したい」という意欲があれば、ご相談いただけます。
夜尿症はストレスのせいでしょうか?親が悪いのですか?
「夜尿症は子どもの精神的ストレスや親のしつけが原因」と思われる方も多いですが、現在では主要な原因として考えられていません。
ただし、夜尿が続くことでお子様を責めてしまうと、精神的なストレスを与えてしまい、結果的に悪影響を及ぼすことがあります。
焦らず、怒らずに見守ることが大切です。
夜尿症が治らないのは発達障害でしょうか?
夜尿症の原因として発達障害が関与していることもありますが、必ずしも発達障害があるわけではありません。
夜尿症の原因は多岐にわたり、発達障害の有無にかかわらず起こり得ます。
夜尿症の治療は生活習慣の見直し(水分摂取・排尿習慣・便秘の改善)、薬物療法(ミニリンメルトなど)、行動療法(アラーム療法など)を組み合わせて進めます。
お子様の夜尿症でお悩みの方は、一度当院へご相談ください。
発達の特性を考慮しながら、お子様に合った治療法を一緒に考えていきましょう。
夜尿症の薬(ミニリンメルト)を飲むデメリットはありますか?
正しく服用しないと副作用のリスクが高まるため、服用時にはいくつかの注意点があります。
舌の下に置いて水なしで服用し、水中毒や効果の減弱を避けるため、服用前後の飲水を控える(服用2時間前から、できれば翌朝まで)必要があります。
水中毒の症状としては、吐き気、嘔吐、頭痛、めまいなどがあり、その他にもまれですが、発熱、肝機能異常などの副作用が報告されています。
これらの症状が現れた場合は、当院へご相談ください。
夜尿があるのでオムツを履かせてもよいでしょうか?
夜尿症に対して、オムツとパンツのどちらを使用しても、治療効果に大きな差はありません。
お子様の気持ちやご家庭の状況に合わせてお選びください。
オムツには、寝具の汚れや洗濯物を減らし、お子様に安心感を与えるメリットがあります。
一方、パンツはトイレへ行く習慣づけを促し、成長を実感させる喜びにつながるでしょう。
いずれの場合も、お子様の成長を温かく見守ることが大切です。
不安やご心配があれば、当院へお気軽にご相談ください。