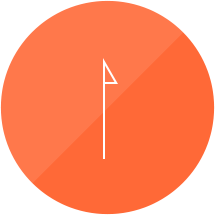「溶連菌」とは
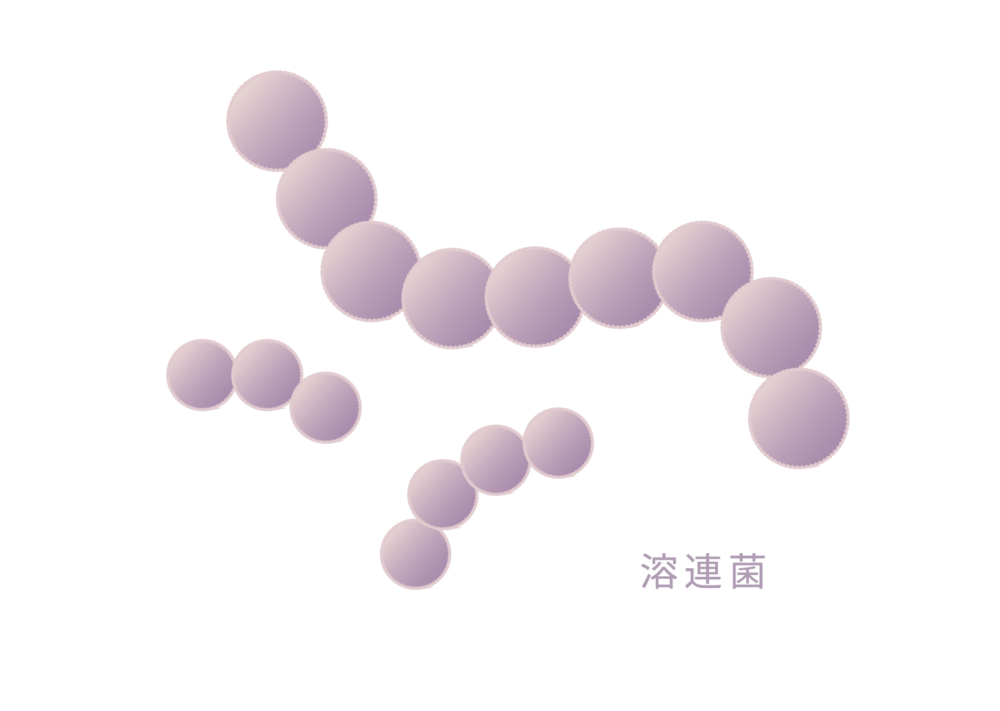 溶連菌感染症は、発熱やのどの痛みを主な症状とする病気で、例年冬から春にかけて流行します。
溶連菌感染症は、発熱やのどの痛みを主な症状とする病気で、例年冬から春にかけて流行します。
しかし、流行時期以外でも溶連菌に感染する可能性があります。
特に保育園児、幼稚園児、小学生に多く見られ、一度感染しても繰り返し罹患することがあります。
溶連菌の症状
溶連菌感染症は3歳から10歳のお子様が罹患しやすい病気ですが、大人が感染することもあります。
小児と成人では症状が異なる場合がありますが、「のどの痛み」「発熱」「首のリンパ節の腫れ」は共通の主要症状です。
潜伏期間は2日から5日程度で、嘔吐、下痢、頭痛、倦怠感などを伴うこともあります。
風邪の症状と似ているため、鑑別が難しいこともありますが、下記のような特徴がある場合、溶連菌感染症の可能性が高くなります。
共通の症状

- のどの痛み
- 38度以上の発熱
- 首のリンパ節の腫れ
- 咳やくしゃみは少ない
- 扁桃腺の腫れや白い付着物
- 嘔吐・下痢・頭痛・倦怠感を伴うこともある
子どもに現れる症状・特徴
- イチゴ舌:舌にイチゴのようなブツブツが現れる。
- 猩紅熱:全身に赤く小さな発疹が出現し、かゆみや腫れを伴う。
- 丹毒・蜂窩織炎:皮膚に炎症が起こり、赤く腫れ上がり、押すと痛みを伴う。
- とびひ:水ぶくれが膿に変わり、掻くことで広がる。
皮膚の症状・湿疹
- 顔がむくんでいる
- 尿量が少ない、または出にくい
- 呼吸が苦しそう
- 顔色が悪い
- 動悸や息切れがある
溶連菌の原因
溶連菌はどうやって
うつる?感染経路
溶連菌感染症は、咳やくしゃみによる飛沫感染や、手やおもちゃなどを介した接触感染で広がります。
感染力が強いため、家族内感染にも注意が必要です。
手洗い、うがい、マスク着用で感染予防に努めましょう。
潜伏期間
感染後2~5日程度で症状が現れます。
流行する季節
11月~4月にかけて流行が活発になり流行するため、注意が必要です。
溶連菌の検査方法
溶連菌感染症の検査は簡便で、迅速に結果が分かります。
のどの粘液を綿棒で採取し、約10分で判定できます。
ただし、重症の場合は合併症の有無を確認するため、追加の検査が必要となることがあります。
合併症の検査
溶連菌感染症後の合併症として「急性糸球体腎炎」があります。
抗原(溶連菌)と抗体が腎臓の糸球体基底膜に沈着し炎症を起こすことで発症することがあるため、溶連菌感染後約2-3週間後に尿検査を行います。
身体のむくみや尿量の減少、褐色尿などの症状が現れた場合は、速やかに当院を受診してください。
溶連菌感染症の治療方法
抗菌薬の服用
 溶連菌感染症には抗菌薬(ペニシリン系など)を用いた治療を行います。
溶連菌感染症には抗菌薬(ペニシリン系など)を用いた治療を行います。
抗菌薬の服用により、24時間以内に溶連菌をほぼ死滅しますが、合併症を予防するために10日間の内服継続が必要です。
副作用として、腸内細菌のバランスが崩れ、下痢を起こすことがあります。
その際は、医師に相談し、整腸剤を処方することも可能です。
溶連菌感染症を予防するには
 溶連菌の感染症予防の基本は、うがいと手洗いです。
溶連菌の感染症予防の基本は、うがいと手洗いです。
お子様は好奇心旺盛でさまざまな物に触れるため、手に細菌やウイルスが付着しやすくなります。
外出後や食事・おやつの前には、石鹸やハンドソープで丁寧に手を洗いましょう。
よくあるご質問
溶連菌はどこにいるのですか?
溶連菌は健康な人の皮膚や咽喉にも存在します。
咽喉に溶連菌を保有していても元気な子供は多く(3割程度との報告も)、こうした症状のない人を保菌者と呼びます。
菌が増殖し、発熱や咽喉頭痛などの症状が現れた場合、感染者と診断されます。
溶連菌に感染したら出席停止ですか?
溶連菌感染症は多くの地域で出席停止の対象となります。
学校保健安全法では「第三種学校伝染病」に指定されており、「適正な抗菌剤治療開始後 24 時間を経て全身状態が良ければ登校可能」とされています。
当院では、治療開始後24時間以上経過し、全身状態が良好であれば登校許可書を発行しますので、許可書が必要な場合はご相談ください。
溶連菌に気付かず放置してしまうとどうなりますか?
溶連菌感染症の初期症状は発熱やのどの腫れなど風邪に似ており、自然治癒することもあります。
しかし、未治療の場合、急性糸球体腎炎などの合併症を引き起こしたり、他者への感染リスクが高まります。
幼稚園や学校などで流行している時期に風邪症状が見られたら、速やかに当院を受診してください。
溶連菌は大人にもうつりますか?
溶連菌感染症は子供特有の疾患と思われがちですが、感染力が強く、大人への感染も起こり得ます。
主な感染経路は飛沫感染で、咳やくしゃみを介して感染が広がります。
主な感染経路は飛沫感染で、咳やくしゃみなどにより周囲に感染します。
大人の場合、のどの痛みに加えて頭痛を伴うことが多く、関節痛や倦怠感などの症状も現れます。