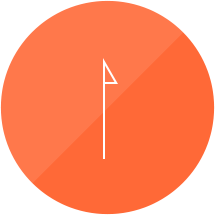初めてお越しの方へ
持ち物
当院を受診される際は、以下のものをお持ちください。
- 母子手帳
- 健康保険証、乳児医療証
- オムツ(必要な場合)
- 診察券
- おくすり手帳
- アレルギーが疑われる食品のパッケージ
(アレルギーの診察の場合) - 他医療機関からの紹介状、検査結果(必要な場合)
- 誤飲が疑われる物と同じもの(誤飲の診察の場合)
- 必要な書類(公費による予防接種・乳幼児健診の場合)
当院からのお願い
- 当院では、スムーズな診察のためWebまたはお電話でのご予約をお願いしております。
- 直接のご来院も可能ですが、お待ちいただくことがあるため、ぜひ予約システムをご利用ください。
- 予防接種は予約優先制のため、事前にご予約をおすすめいたします。
- 予約いただいた場合でも、緊急度や混雑状況により、診察順が前後する場合があります。
- 予約無しでも接種可能ですが、在庫が無い等でお断りする場合があります。
ご協力をお願いいたします。
小児科
診療する疾患・症状
発熱
発熱は体が感染症などに対抗するために体温を上げる反応で、一般に37.5℃以上の体温のことを指します。
発熱の原因には、感染症(かぜ、インフルエンザ、細菌感染症など)やワクチン接種後の副反応、熱中症、川崎病や自己免疫疾患などが考えられます。
熱が長引く場合や、発熱や咳などの風邪症状以外を伴う場合は、速やかに受診しましょう。
咳・鼻づまり・鼻水
原因として、風邪やアレルギー、乾燥などが考えられます。部屋を加湿して乾燥を防ぎ、こまめな水分補給を心がけましょう。呼吸を苦しそうにしていたり、夜眠れなかったり、黄緑色や粘り気のある鼻水が出る場合は、放置せずにご相談ください。
下痢・嘔吐・腹痛
お子様に腹痛・嘔吐・下痢の症状が現れた際は、消化不良のほか、ウイルス感染(ロタウイルス、ノロウイルスなど)や細菌感染(食中毒)、アレルギーが疑われます。
感染症の場合は、下痢や嘔吐がウイルスなどを外に出すための症状なので自己判断での服薬は控えましょう。また脱水症状にならないよう、こまめに水分補給をし、消化の良いものを食べさせてあげましょう。症状が改善しない場合は、早めにかかりつけ医を受診してください。
便秘
排便の回数が週3回以下と少ない、便を出しにくい、出すときに痛みを伴う状態を指します。
食生活や生活習慣、心理的な問題が原因となっていることが多いですが、腸に問題がある可能性もあります。便秘が癖づくと、大人になっても改善が難しいこともありますので、排便時に辛そうにしていたり、頻繁にお腹が痛くなったりする場合は、お早めにご相談ください。
ブツブツ・腫れ
お子様にブツブツや腫れができる原因は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー症状のほか、水ぼうそう・手足口病・風疹・はしかなどの感染症、あせもや虫刺されなどが考えられます。
原因によって適切な対処法や治療法が異なりますので、まずはご相談ください。
乳児湿疹
生後1か月~1歳ごろに多く見られる肌の炎症(赤み、かゆみ、ブツブツ、水ぶくれ、かさぶた)を指します。赤ちゃんのお肌は大人に比べてとてもデリケートなため、乾燥や汗、摩擦などが刺激となり、炎症が起きると言われています。多くの場合は自然に治癒しますが、最近は乳児湿疹によって皮膚のバリア機能が低下し、アレルギーの原因となる可能性が指摘されています。症状が広がったり、赤みが強くなったりした場合は、ぜひ当院にご相談ください。
不機嫌・元気がない
子どもは体調が悪くても、自分で言葉にしてうまく伝えられないことがあります。特に生後3か月頃までの赤ちゃんで、食欲がない、泣き止まない、元気がないなど、いつもと違う場合は、ご相談ください。
また、呼びかけても目線が合わない、反応が薄い、ぐったりして顔色が悪いといった症状が見られる場合は、速やかに受診しましょう。
頭痛
頭痛にはいくつかのタイプがあり、それによって対処法が異なります。そのため、症状や原因を正しく特定したうえで治療を行います。頭痛の頻度や起こる状況、伴う症状をできるだけ詳しくお伝えください。
また、CT検査やMRI検査などの画像検査が必要と判断された場合は、適切な医療機関へご紹介いたします。
低身長
平均身長と大きな差がある場合や、身長の伸びが悪い場合は、成長ホルモンや甲状腺ホルモンの異常、染色体の異常、骨や臓器の病気が関係している可能性があります。お子様の身長の伸び方が気になる方は、お気軽にご相談ください。
溶連菌
溶連菌感染症は、A群β溶血性連鎖球菌という細菌によって引き起こされる感染症です。主にのどに感染することで起こる病気で、特に学童期の子どもによく見られます。
主な症状として、高熱や激しいのどの痛み、発疹、イチゴ舌(したが赤くブツブツする状態)などが現れます。
マイコプラズマ感染症
マイコプラズマ感染症は、マイコプラズマ・ニューモニエ(Mycoplasma pneumoniae)という細菌が原因で起こる感染症です。特に小児や若年層に多くみられ、咳や発熱、全身の倦怠感などの症状が特徴です。
新型コロナウイルス
新型コロナウイルス感染症は、大人だけでなく子どもも感染する可能性があります。子どもでは、発熱、咳、のどの痛みなど、風邪のような症状として現れることが多いですが、基礎疾患があるお子様や新生児、免疫が低下しているお子様は重症化のリスクがあるため、注意が必要です。
おたふくかぜ
おたふくかぜは、ムンプスウイルスが原因で起こる感染症で、正式には「流行性耳下腺炎」と呼ばれます。主な症状は、耳の下にある耳下腺の腫れと痛みで、発熱や全身のだるさ、食欲不振、関節痛を伴うこともあります。
ワクチン接種で予防することが可能です。
アレルギー科

当院では、食事後に湿疹が出る、咳や鼻水が長引くなど、アレルギーが心配なお子様のアレルギー検査や治療を行っています。
週1回(毎週水曜日)、日本アレルギー学会指導医・専門医である田中裕也先生(当院の医療法人理事長)によるアレルギー診療・指導も実施しています。アレルギーに関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
診療する疾患・症状
食物アレルギー
食物アレルギーとは、特定の食物を食べたり触ったりすることで免疫システムが過剰に反応し、さまざまな症状を引き起こす疾患です。
乳幼児期に多く見られますが、成長とともに自然に改善することが多い一方で、重度の場合は成人しても症状が続くことがあります。適切な診断と治療が重要です。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、慢性的な皮膚の炎症が続き、かゆみと湿疹、そして乾燥を繰り返すのが特徴です。遺伝的な要因や環境要因が関与し、幼少期から大人まで、生涯にわたって症状を繰り返すことがあります。適切なスキンケアや外用療法で行うことで、しっかりと症状を改善させることが大切です。
気管支喘息
気管支喘息は、気管支(空気の通り道)に炎症が起こり、狭くなることで呼吸がしづらくなる病気です。乾いた咳や痰、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という呼吸音(喘鳴)、息苦しさなどの症状が現れます。根気よく治療を続けることによって、症状を完全にコントロールすることが大切です。
花粉症
花粉症は、大人だけでなく、子どもにも多くみられるアレルギー疾患です。スギ花粉が代表的ですが、ヒノキ、ブタクサ、ヨモギなど、さまざまな花粉が原因となります。
症状が強いと、日常生活や学業・仕事に影響を及ぼすことがあるため、早めの治療が重要です。
適切な治療を行うことで、重症化を防ぎ、他のアレルギー疾患のリスクを抑えることができます。
ダニアレルギー
ダニの死骸やフンを吸い込むことで起こるアレルギー反応です。特に、屋内で一年を通して症状が出ることが多く、アレルギー性鼻炎や気管支喘息などの原因となることがあります。
蕁麻疹(じんましん)
突然、皮膚の一部が赤く盛り上がり、かゆみを伴う「膨疹(ぼうしん)」と呼ばれる症状が現れる疾患で、短時間で消えるのが特徴です。
アレルギーのほか、物理的な刺激、ストレス、ホルモンバランスの変化などが関与するといわれています。
原因を特定するために、アレルギー検査を行うことがあります。
アナフィラキシー
アナフィラキシーは、特定の物質(アレルゲン)に対し、体が過敏に反応することで全身に激しいアレルギー症状が現れる状態です。
数分~数時間以内に、複数の臓器(皮膚、呼吸器、循環器、消化器、神経系など)に重篤な症状が出ることがあり、命に関わる危険性もあるため、早期治療が必要です。
症状に応じて、アドレナリン筋肉注射、抗ヒスタミン薬、ステロイド剤の投与などを行います。
腎臓内科
 当院の院長は腎臓専門医・指導医であり、お子様の夜尿症や検尿異常に対する検査・治療を行っています。
当院の院長は腎臓専門医・指導医であり、お子様の夜尿症や検尿異常に対する検査・治療を行っています。
お子様のおしっこに関するお悩みや気になる症状がございましたら、お気軽にご相談ください。
診療する疾患・症状
夜尿症
夜尿症は、5歳を過ぎても月に1回以上、夜間の睡眠中に無意識に尿を漏らしてしまう状態を指します。
夜尿症の原因は完全に解明されていませんが、膀胱機能の未発達、ホルモン分泌の異常、遺伝、睡眠障害、ストレス、生活習慣など関与しているとが考えられています。
夜尿症は適切な対策・治療によって改善することが多いため、お一人で悩まずご相談ください。
当院では、お子様に合わせた治療を行っております。
学校検尿異常
学校検尿で、「蛋白尿」「血尿」「尿糖陽性」などの異常を指摘された場合、必ずしも病気とは限りませんが、詳しい検査が必要なことがあります。
尿異常の原因には、一時的なものと病気が関係しているものがあり、慎重な判断が求められます。
再検査を行い、病気の可能性が高い場合は、さらに詳しい検査を実施し、必要に応じて適切に専門医療機関(兵庫県立こども病院など)へご紹介いたします。
おしっこが出ない・
頻繁におしっこに行く
おしっこの回数や量の変化は、体調や腎・膀胱の状態を反映する重要なサインです。
おしっこが出にくい場合、水分不足のほか、腎臓や尿路(おしっこの通り道)、神経、筋肉の異常が関与している可能性があります。
一方で、おしっこの回数が異常に多い場合は、過活動膀胱、尿路感染症、糖尿病などの疾患や、ストレス・不安が影響していることが考えられます。
尿路感染症
尿路感染症とは、尿道、膀胱、尿管、腎臓など、尿の通り道に細菌やウイルスが感染し、炎症を引き起こす病気です。
特に女の子や乳幼児に多くみられ、発熱が続く場合は、尿路感染症の可能性を考慮する必要があります。
適切な抗菌薬治療を行わないと腎臓に影響を及ぼすことがあるため、早期の診断と治療が重要です。
ネフローゼ症候群
ネフローゼ症候群は、腎臓の糸球体という部分が障害され、尿中に大量のタンパク質が漏れてしまう病気です。
その結果、全身にむくみが生じたり、免疫力が低下したりといったさまざまな症状が現れます。
ネフローゼ症候群の治療は、ステロイド療法が基本となります。ステロイドは種々の副作用が問題となりうることから、治療開始時は入院が必要となるのが一般的です。
当院では、必要に応じて適切な専門医療機関(兵庫県立こども病院など)へご紹介いたします。
初期症状としてはまぶたの腫れや尿の泡立ちとして現れることがありますので、気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください